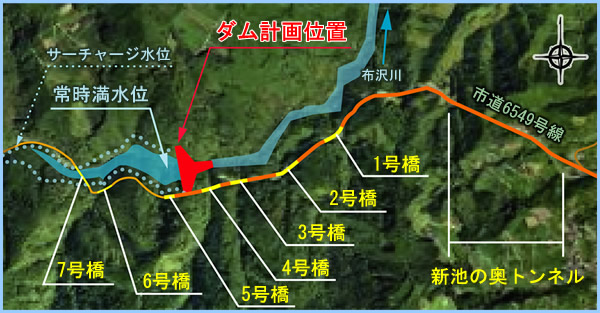【15年3月14日探索・5月6日公開】
現在地はここ
公園らしい場所になった。
「ぽっぽ通り」的にはここがやすらぎの広場で、このすぐ先が青春の広場という事になっている。
なぜか、自転車に似た遊具が設置されていた。
「ぽっぽ通り」的にはここがやすらぎの広場で、このすぐ先が青春の広場という事になっている。
なぜか、自転車に似た遊具が設置されていた。
動輪の展示もあった。
本当に動輪だけであるのと、東野鉄道に関係ある機関車のものであるのかが不明なのが気になった。
本当に動輪だけであるのと、東野鉄道に関係ある機関車のものであるのかが不明なのが気になった。
割愛するが、ちなみに青春の広場にはいくつかのオブジェがあった。
もうすぐぽっぽ通りは終わりになる。
ん!!右に何かがあるぞ!!
ん!!右に何かがあるぞ!!
キロポストであるようだが、明らかに東野鉄道のものでない事がすぐにわかってしまう。
そもそも200mという半端な距離にこんな立派なキロポストは必要ないし、200mと0.2KMという表記も見かけた事がない。
第一、起点からは既に4kmを越えているのでこの200mは大田原側を起点とした「ぽっぽ通り」の距離標という事らしい。
そもそも200mという半端な距離にこんな立派なキロポストは必要ないし、200mと0.2KMという表記も見かけた事がない。
第一、起点からは既に4kmを越えているのでこの200mは大田原側を起点とした「ぽっぽ通り」の距離標という事らしい。
終点のゲートが見えてきた。
ちなみに、ここは「であいの広場」らしい。
ちなみに、ここは「であいの広場」らしい。
県道53号線を渡ると、廃線跡は普通の道路になっていた。
そして、大田原駅は先の建物の場所らしい。
現在地はここ
スーパーマーケットであったはずなのだが、既に閉店し、撤退していた。
テナント募集の横断幕が物悲しい。
廃駅跡に建てられたスーパーも撤退したという事は、この場所には廃の主でもいるのか??
廃駅跡に建てられたスーパーも撤退したという事は、この場所には廃の主でもいるのか??
ちなみに、テナントの問い合わせ先は東野交通だった。
そのまま2車線の道路はまっすぐに進むが、龍泉寺のところで道は90度のカーブを描く。
廃線跡は寺の参道によって遮られたが・・・
廃線跡は寺の参道によって遮られたが・・・
その、反対側に来た。
車が2台停まっているが、その先は・・・
車が2台停まっているが、その先は・・・
舗装が終わり・・・
俄然、廃線跡らしくなってきた。
一気にテンションが高まってきた。
一気にテンションが高まってきた。
(その4・最終回につづく)